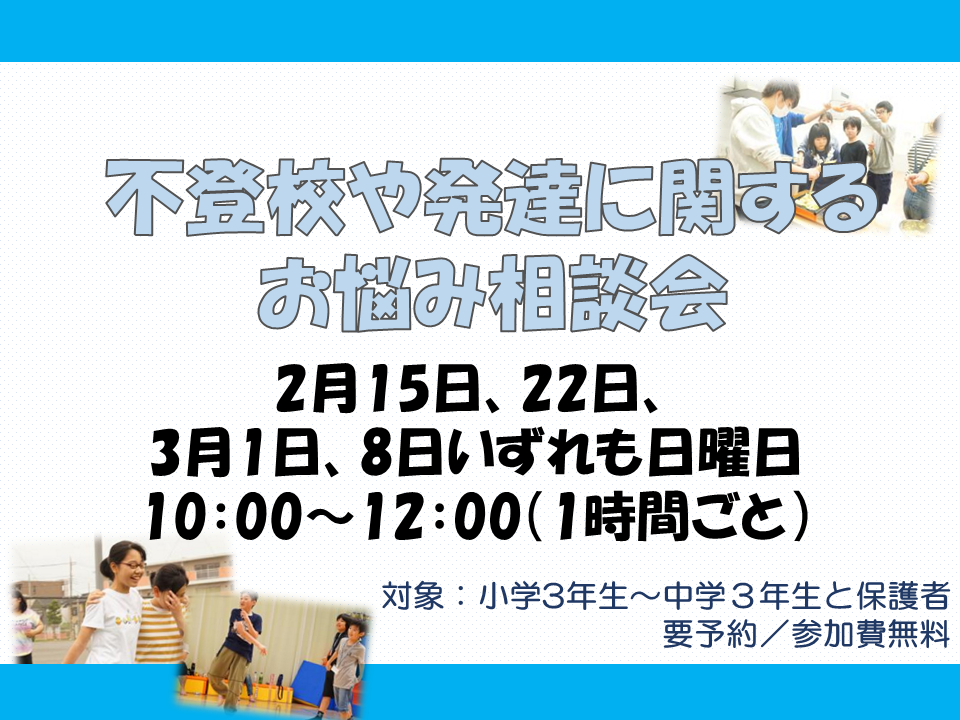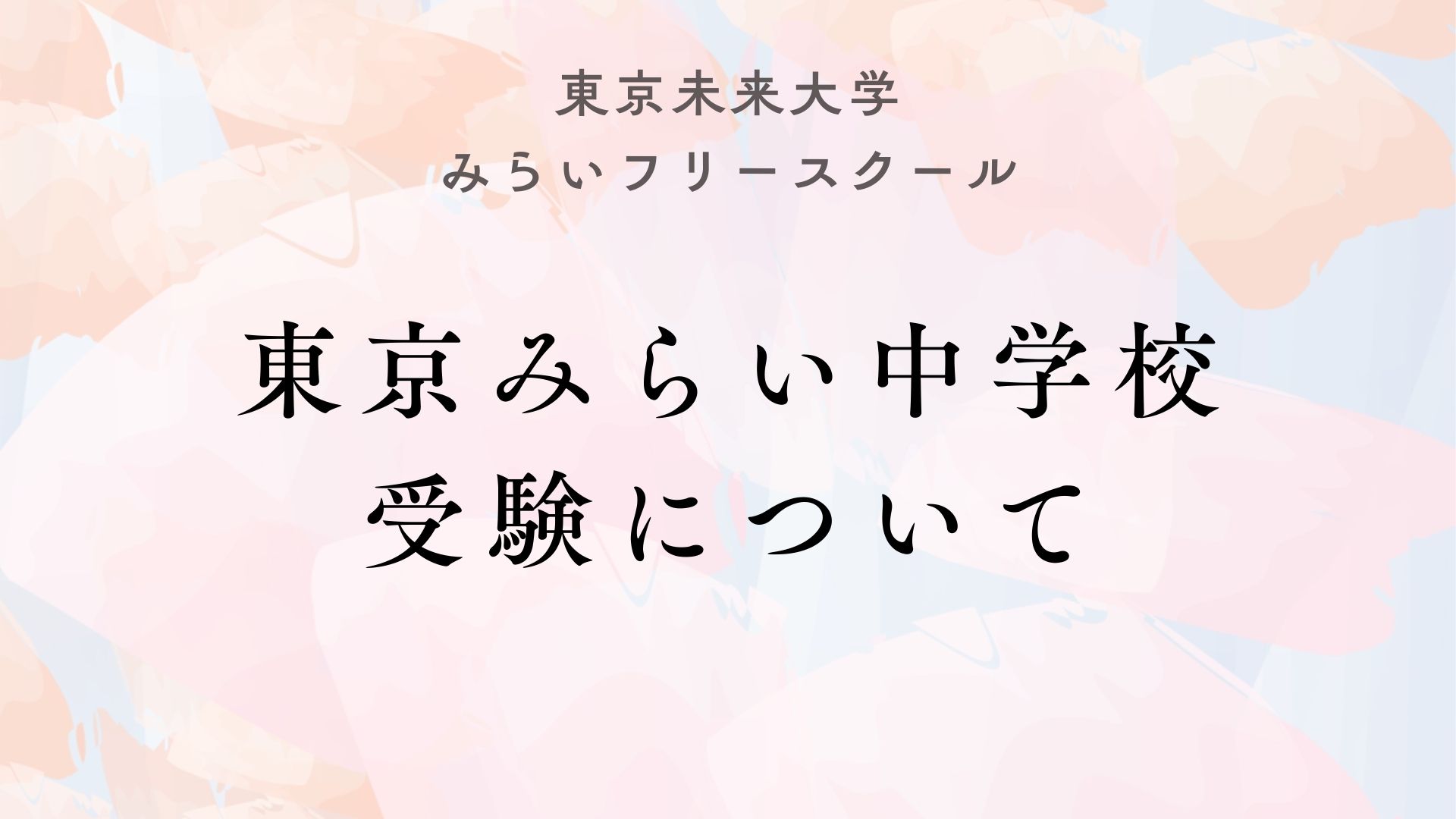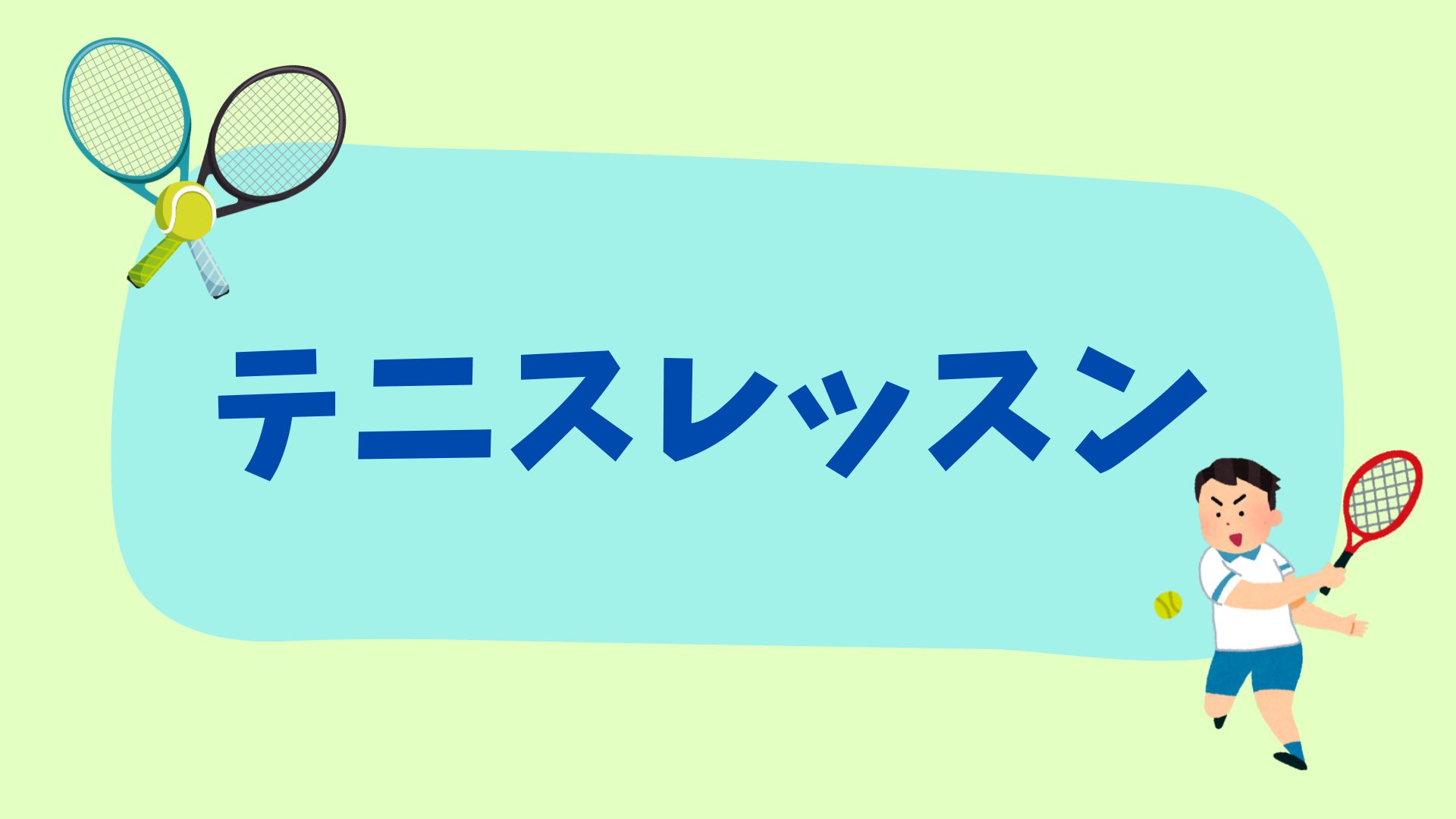ニュース
○ADHDの特性に合わせた勉強法を取り入れよう
ADHDと一口に言っても障害特性は子どもによってさまざま。一般的には「不注意優勢型」「多動性・衝動性優勢型」に分けられると考えられていますが、両方の特性を持ち、どちらともいえない「混合型」もあります。今回は、ADHDの障害特性ごとの勉強法を考えてみましょう。
○不注意優勢型の場合
気が散りやすく、集中力を保つのが難しい不注意優勢型。勉強するときには、気が散る要因になるものをできるだけ取り除くことが大切です。たとえば、部屋はできるだけ片づけ、気になるものが目につかないようにしておきます。体が壁向きになるように机を配置する、問題集はできるだけシンプルなものを選ぶというのもおすすめです。問題集はページ数や問題数がたくさんあるとやる気がそがれるため、プリント形式で1枚ずつできるものなどがよいかもしれません。また、注意を引き戻すために声をかけるのが効果的なこともあります。家庭だと気になるものが多い場合は、学習塾などに通うのも一つの方法です。環境を変えることで勉強モードに切り替えられることもあります。
○多動性・衝動性が目立つ場合
すぐに体を動かしたくなり、その衝動を抑えることができないのが、多動性・衝動性の特徴です。勉強中にも関わらず、立ち歩きがやめられなかったり、声が出てしまったりといった症状に困っていることもあるのではないでしょうか。このタイプの場合、「動いてはいけない」と強制すると、逆にストレスになることがあります。「立ち歩いてもよいが、すぐ戻る」「声を出したくなったら離席する」などルールを決めるとよいでしょう。また、音楽を聴いたり、何か物を触ったりしながら勉強した方が集中できるという子もいます。集団で勉強するよりも、少人数や家庭内で自分で勉強するほうが向いているといえるでしょう。
○どちらにも有効!時間を区切って学習する
集中力が散漫になりやすく、長時間の学習に耐えられないというのは、どちらのタイプにもある程度共通することです。ADHDには「不注意優勢型」「多動性・衝動性」に加えて、「混合型」もあります。一概にどちらかのタイプに分けることができず、両方の特性を持っている子もいるでしょう。学習の際のコツは、短時間の勉強を積み重ねることです。はじめは、10分や15分などのごく短い時間でも構いません。プリント1枚、問題1問でも構わないので、決められた時間集中して取り組めることが大切です。この際、タイマーなどを自分でセットさせると、時間意識を持ちやすくなります。また、同じ科目を勉強し続けるよりも、細目に科目を切りかえた方が効果的な場合もあります。