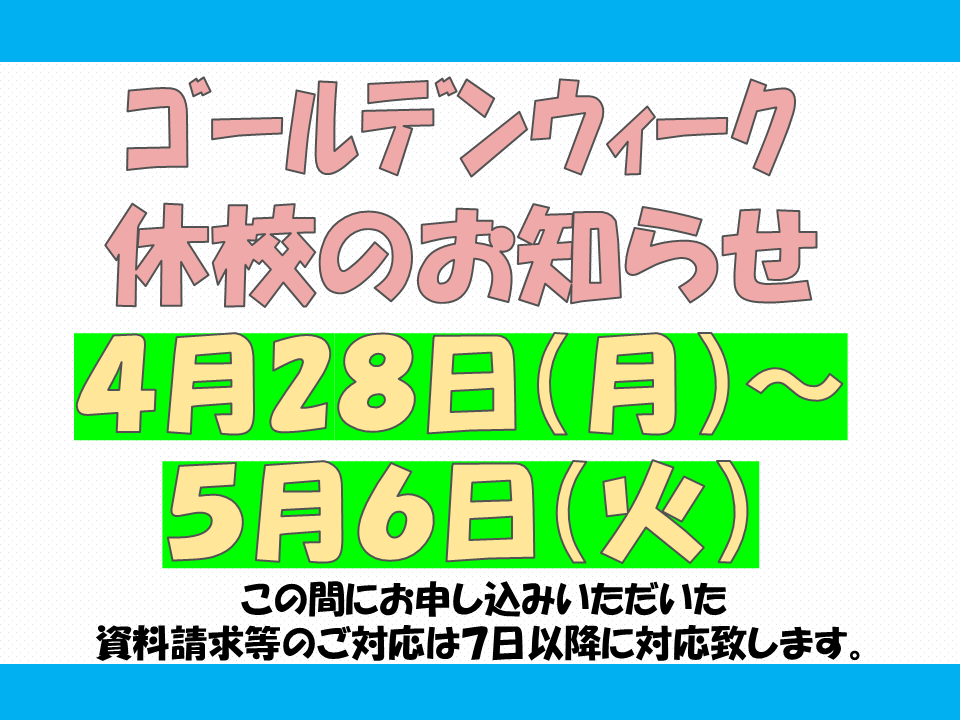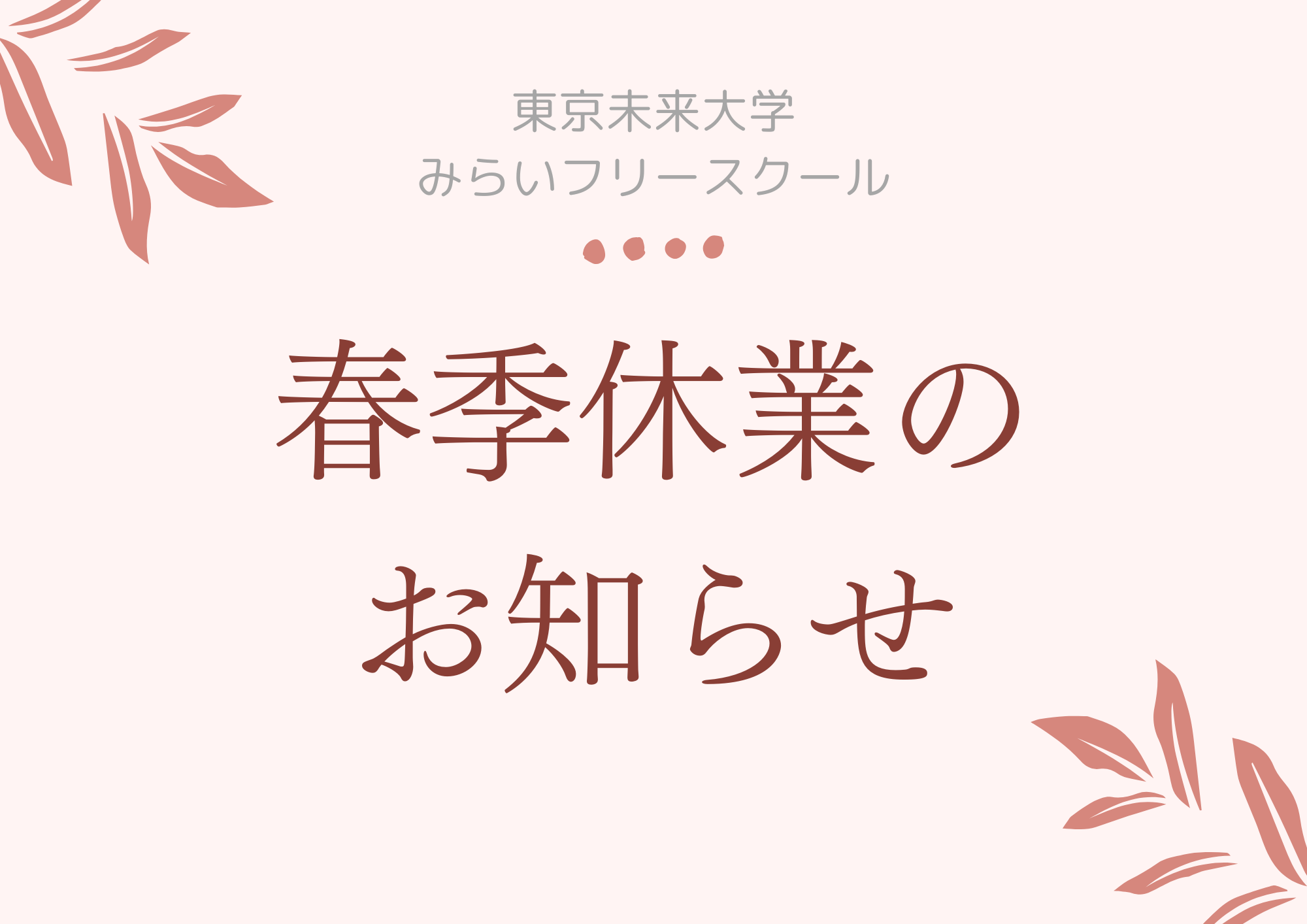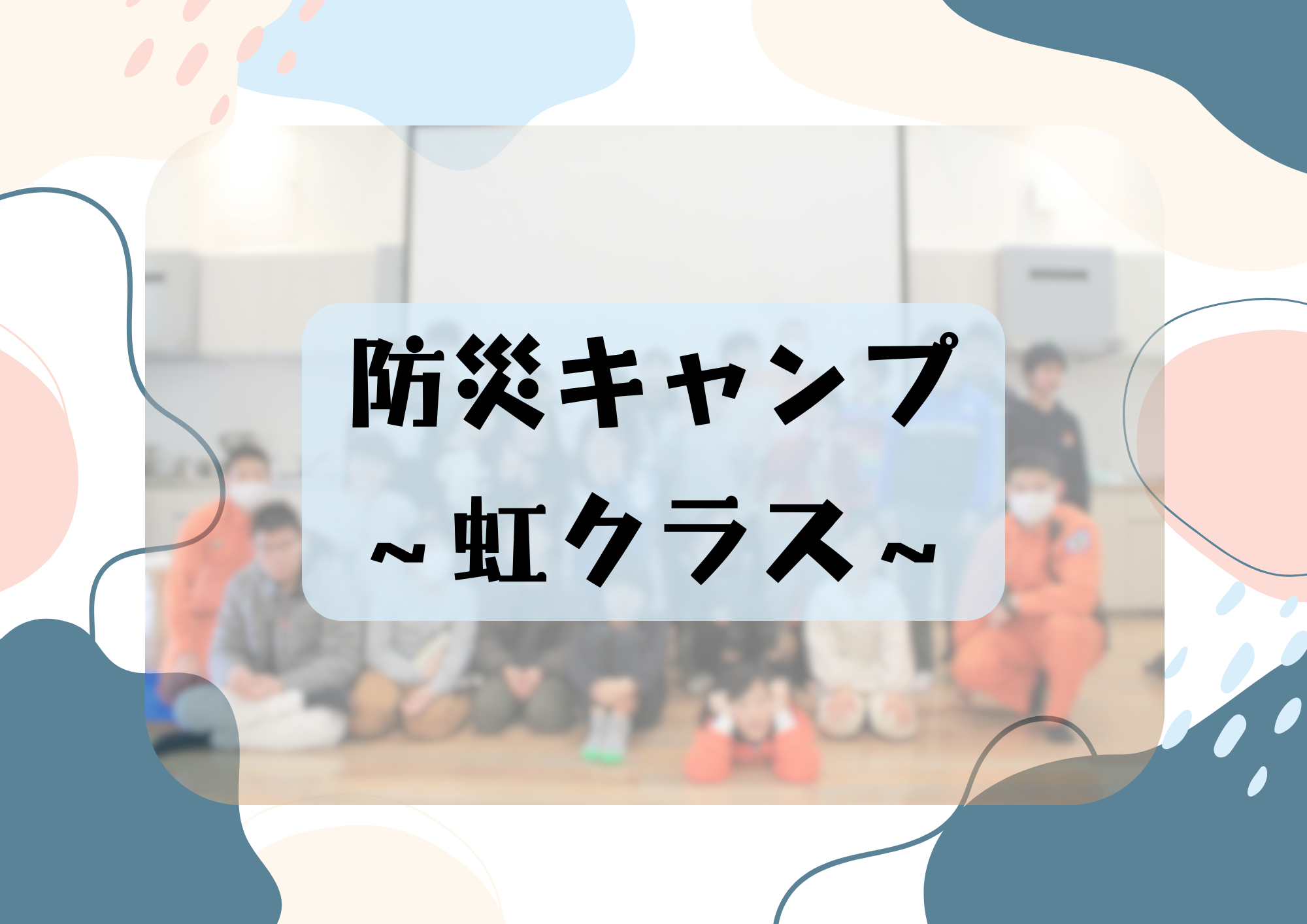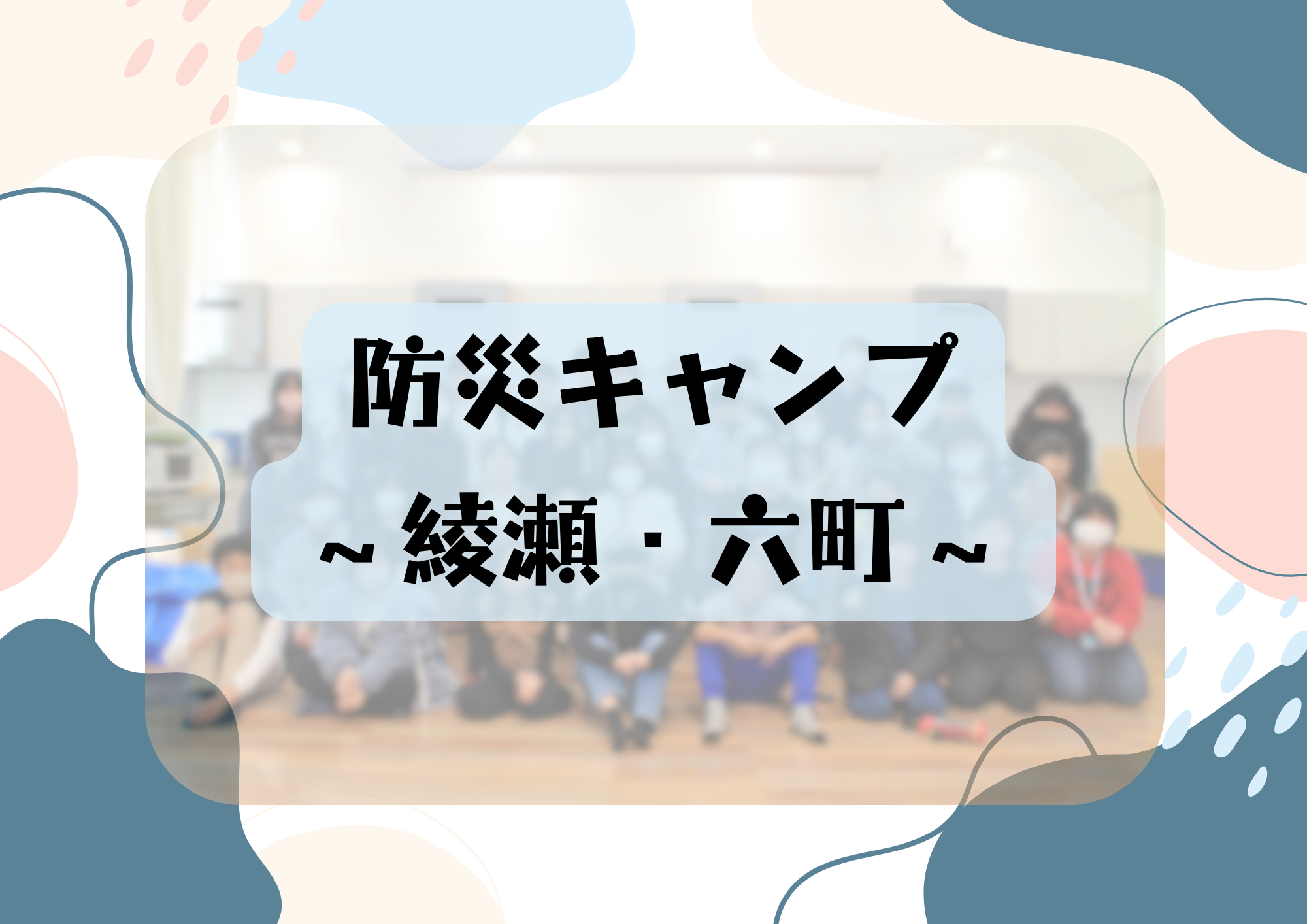ニュース
(1) 文章問題を解くのに必要な能力分析
算数の学習の中で、文章問題は苦手な子どもも多く、なんとかしなければと思われるケースが多いと思います。
しかし、文章問題の支援はなかなか効果が上がらないことも多く、今の学年では出来るようになっても次の学年の新たな文章問題で、またつまずいてしまうということもよくあります。
算数の問題を解くためには
①数概念形成(基数性・序列性)
②継次処理能力、同時処理能力
③視覚認知、聴覚認知
④言語の発達、偏り
⑤ワーキングメモリ機能、記憶
⑥プランニング
⑦注意、集中
という能力が必要です。
例えば、九九の習得には、聴覚認知能力、ワーキングメモリ、記憶などの能力が必要だと考えていきますが、文章問題では、上記に挙げた全ての能力が関わっていると考えなければなりません。様々な能力のうちのいくつかが欠けただけで、文章問題を解くことが難しくなるため、たくさんの子ども達がつまずくという結果になっています。
(2) 文章問題を解くプロセス
このような様々な能力を使って文章問題を解いていますが、文章問題を解く際には、次のようなプロセスを通って解いていきます。
① 語句や文章の内容理解・・・言語の理解能力が関連します。
② イメージ化・・・文で書かれた問題文が映像として頭に浮かんでくることを表しています。言語意識と映像とのマッチング能力が開花します。
③ 立式・・・イメージできた内容に沿って必要な演算方法が選択でき、それに沿って立式することが問われます。継次処理能力や、言語の意味理解能力が関連します。
④ 計算・・・立式に沿って正確に計算する能力があるかどうかが試されます。継次処理能力、同時処理能力、数の概念の理解等が関連します。
⑤ フィードバック・・・計算して出されて答えを書いた時に、その答えは問題で聞かれている内容から見て妥当な大きさの数字かどうか、問題で聞かれている単位と整合しているがどうかなどを検証することです。計算間違いをしたかどうかということもフィードバックの段階でチェックしています。ワーキングメモリ機能や、同時処理能力、論理的に考える能力が関連します。
(3) 文章問題の間違い分析と支援の実際
ここでは、実際に文章問題で間違えた解答の例を紹介します。
《 問題1 文章に表現された内容を理解することが困難な例 》
問)120g入りのさとうを40ふくろつくります。さとうはみんなで何gいりますか。
式) 120+40=160 答え160
文章を読んで内容を理解しておらず、「みんなで」という言葉でたし算と判断してしまう間違いです。
支援のポイント
この問題では、文章の読解の弱さが要因ですから、本質的な対応は言語的な意味理解をどのように伸ばしていくかということになります。このようなタイプの場合、往々にして「みんなで」と書いてあったら「たし算」というようなキーワード法で考えさせていく方法をとります。
しかしこれは、かけ算を習い始めると新たなつまずきの要因になります。かけ算でも「みんなで」という言葉は使われるからです。やはり、言語能力を向上させるトレーニングが必要となります。絵本などから始めて、「文を読んで内容をつかむ」練習を繰り返すことが必要です。
(4) 文章問題の間違い分析のまとめ
解答プロセスに沿った文章問題の間違い分析の例を紹介しました。それぞれの段階の間違いには、他にもいくつかあり、文章問題の間違いの要因には様々なパターンが存在すると言えます。ひとつひとつの要因については、たくさんの文章問題の間違いについて検証することから明らかにしていくことが必要です。
文章問題の間違いの中で、特に根本的な要因への対応が必要です。問題1で紹介した通り、キーワード法では、かけ算でも同じキーワードを使うため、混乱に拍車をかけるだけになります。
また、言語の能力も関連するとなると、算数の授業の中だけで解決することは当然難しくなり、国語での言語指導も算数の文章問題への支援としては必要となります。間違いの分析から見えてきた要因に対応する際には、教科の枠を超えた支援や、認知特性のトレーニング支援が必要となることもあります。