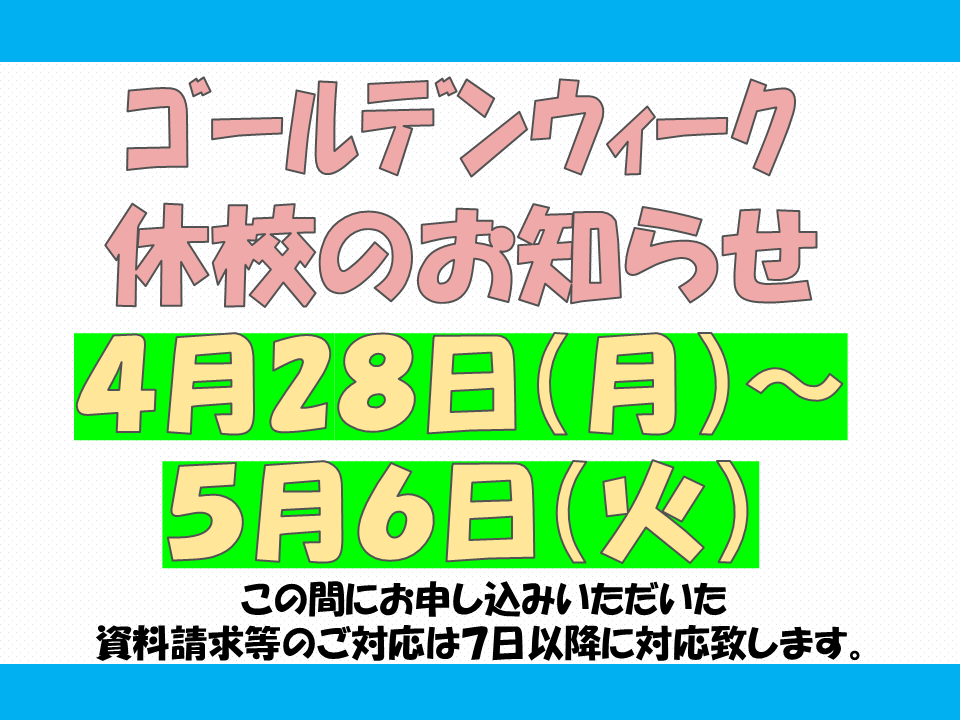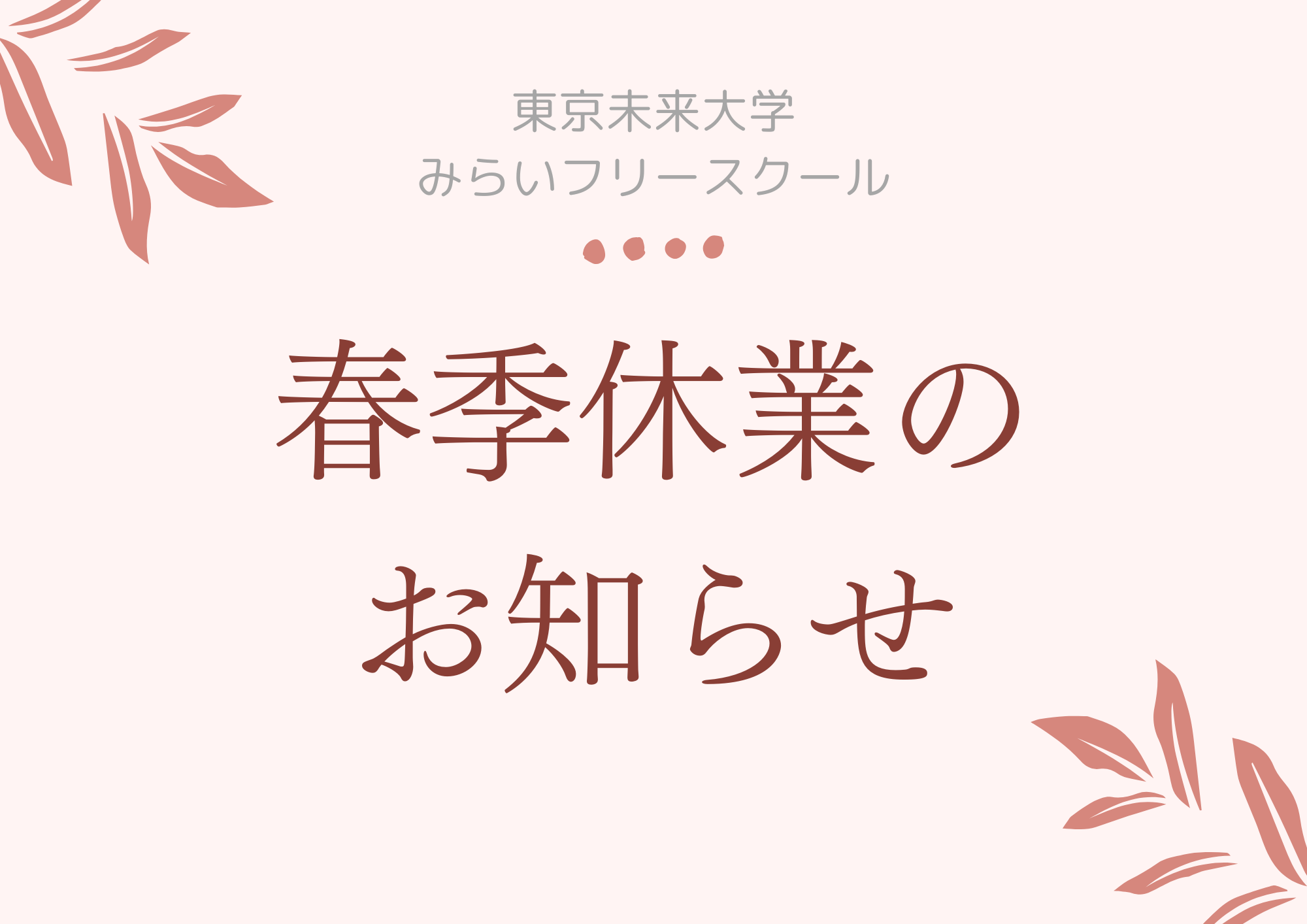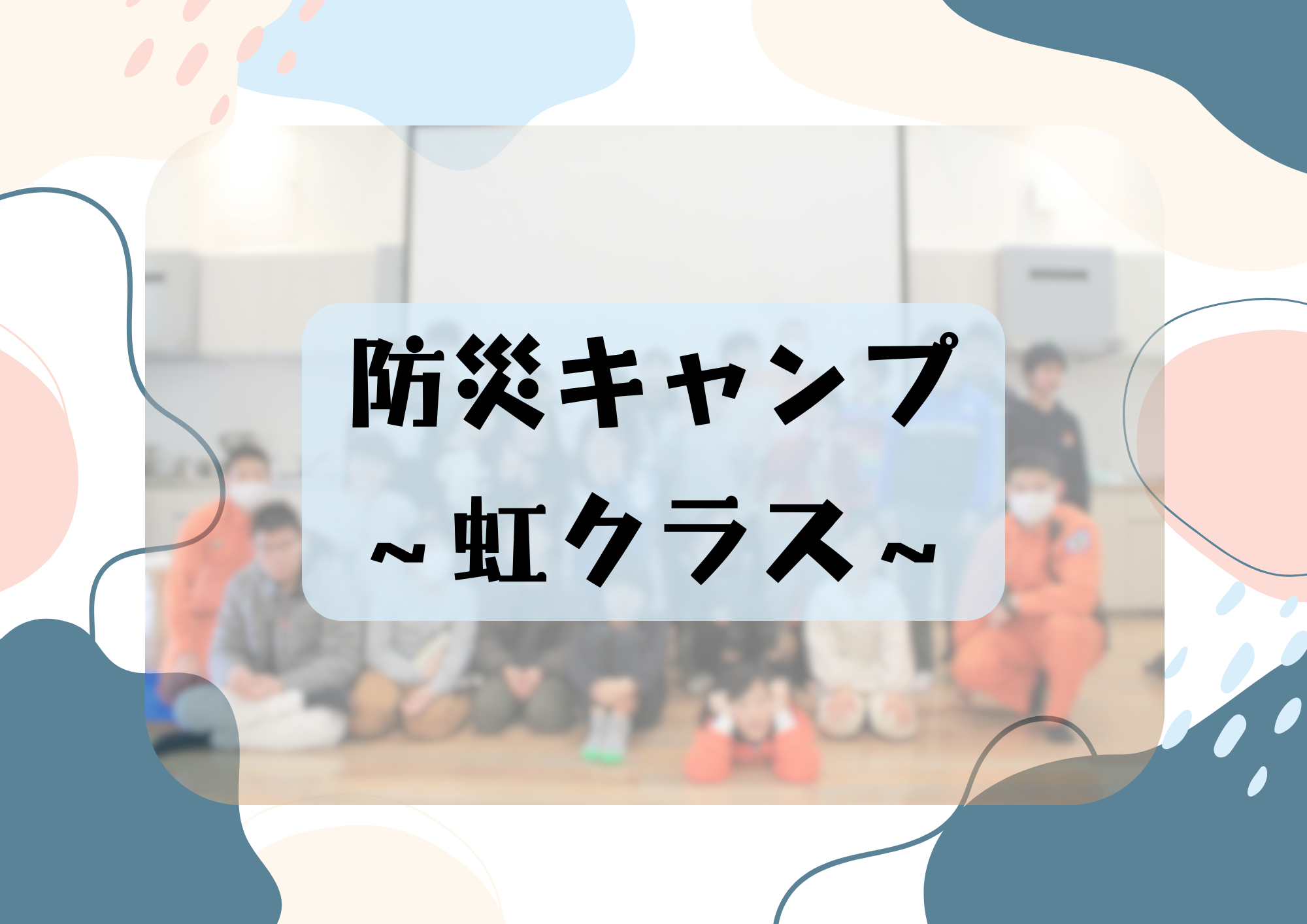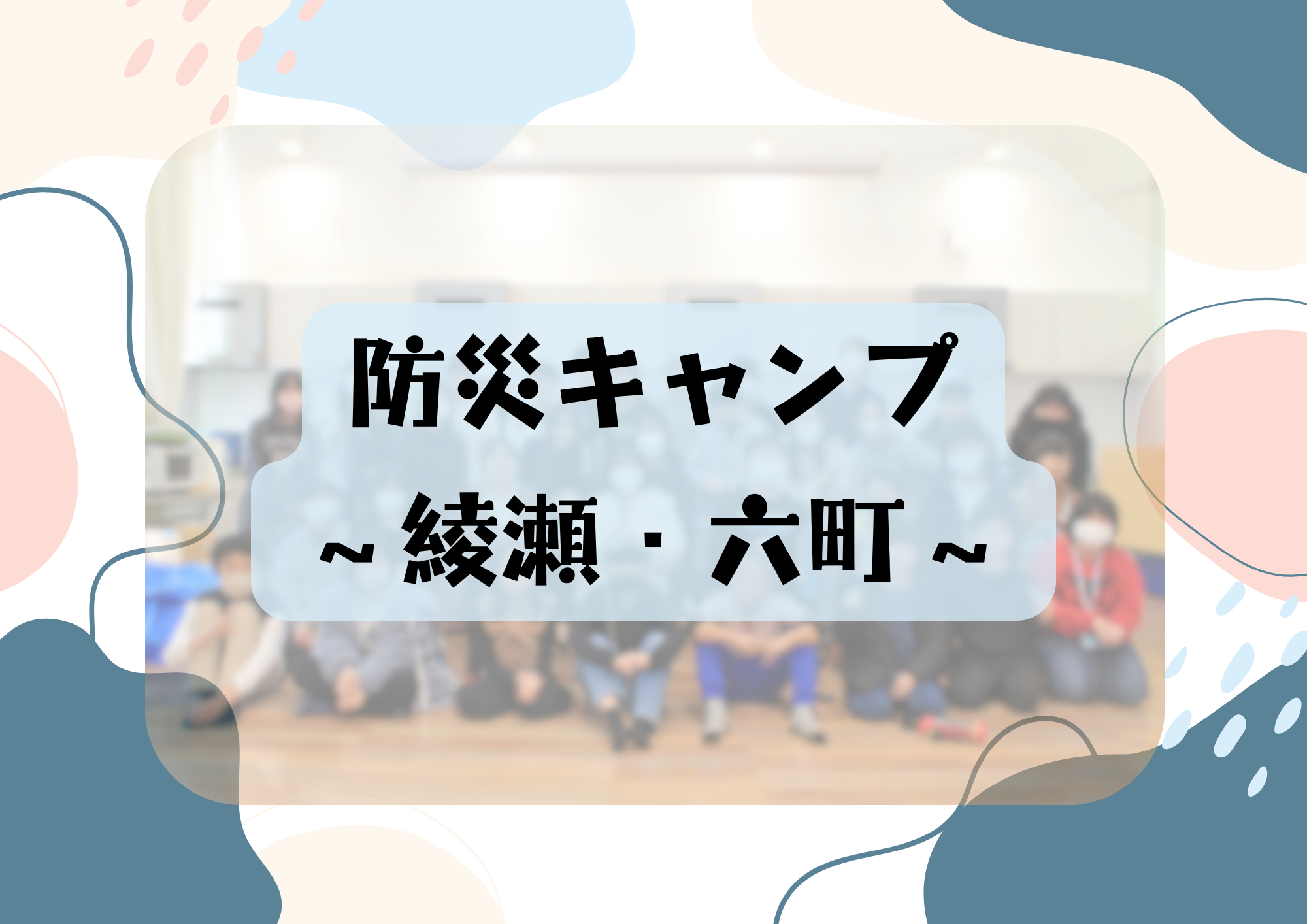ニュース
○読み書きって難しい!
読んだり書いたりすることに難しさを感じるのはどうしてなのでしょうか。同じようなつまずきに見えても、人によって全く違う理由があるかもしれません。同じ問題でも人それぞれ物事の理解の仕方や解決の仕方が違ってきます。その人が文字をどう捉えているのかが、読み書きができるようになる方法を探る大きな手がかりになります。
○段階的に学習する「読む」
「読む」ことはいくつかの段階に分けられます。まずは一文字を読むこと。手のひらサイズのカードに書かれた文字を、見てすぐに声に出して読む練習があります。反射的に反応することを目指すものです。何度も繰り返すことが必要です。目からの刺激と音の刺激を繋げることで、素早く読むことが少しずつ楽になってきます。
次は短い単語を読む練習です。一文字ずつ「み・か・ん」と読むのではなく、「みかん」と一つの繋がった形として覚えて声に出しましょう。単語と一緒にイラストを提示することで、単語をイラストに変換してから音声で出すこともできるようになります。「みかん」「やかん」というように、一文字置き換えた単語を集め、素早く読めるように単語を増やしていきましょう。
その次は文章です。文章を正確に間違えずに読もうとしても、読み飛ばしや読み誤りが起こることがあります。「~しましょう」「~しました」などの文末表現を最後まで読むことなく思い込みで読んでいたり、「つくし」「くつ」など形の似た単語を入れ替えて読んでしまうこともあります。指で示しながら読むようにすることで、読み飛ばしや読み誤りを防ぐヒントにもなります。
○線と線の関係性を捉えて「書く」
「書く」ことが難しい場合、まず平仮名からではなく、平仮名を分解して縦線や横線などの練習から始めましょう。文字の形は線と線との位置関係からできています。上下の関係や左右の関係、中心からのバランス、並行や垂直、交差などそれぞれの線同士が関係しあって一つの文字を作っています。そのためまずは一つの線を引く練習、丸いグルグルの線を書く練習、またそれができるようになればバッテンなど交差した線同士を書く練習をしていきましょう。
○読み書きを習得しやすい方法は人それぞれ
画一的な方法で何度も繰り返すよりも、物事の捉え方を意識した学習方法を提案していくことで、読み書きはずいぶん習得しやすくなります。重要なことは、成果を細かく本人に伝えることです。「わ」と「ね」などの似た文字を書く際には、違いが分かりやすいように書き分けることを目標にします。まずは「見比べる」ことで正しい文字を認識し、似た文字の違いに気づくようにしていきましょう。学習時には今できたこと、今日できるようになったことをその都度わかりやすく本人に伝える必要があります。そうすることで文字を正しく使い分けられるようになり、最終的な目標に近づいていくことを目指せるようになります。